最近の映像制作の現場では、スピード、数、インパクトが求められる傾向が強いように思います。生成AIや低コストな映像ツールの普及により、誰でも手軽に映像を作れる時代においては、「量」や「スピード」「奇抜さ」が目をひく要素と思われるのは否定できないうようにも感じます。
しかし、本当に大事なのは その映像が相手に何を伝えるか。ここを外してしまえば、どれだけ早く安く作っても意味がないように思っています。そこで映像の「伝える」という本質的な部分をレベルアップする為に必要となることをCG屋目線でまとめてみたいと思います。
映像制作の本質は「伝えること」
映像は、「伝えるための手段」です。映像を作ることが目的になっていたとしたら、少しもったいないですね。
映像が欲しい(作りたい)と考える人は、少なからず何かを伝えたいと思っているはずです。文章や言葉だけでは伝えられない何かがあり、映像はその伝達手段のひとつだと思います。
例えば、以下のようなケースが一般的に考えられます。
商品の魅力を理解してもらいたい
企業のブランドを印象づけたい
言葉では伝えづらいことを視覚的に表現したい
映像として記録(後の人に内容を伝えたい)
どれも、見る人に伝わらなければ成立しないものです。しかも、ただ撮るだけでは、これらの内容は伝わることにならないことは多くのクリエイターの皆さんが実感として感じていることでしょう。
つまり、映像を制作する目的は、「伝えるべきことが伝わること」、そして、情報がきちんと整理されていることが重要です。

情報の整理-構成
多くの映像クリエイターは、企画・構成の段階で伝わりやすい設計を心がけています。
見る人の目線を考え、どのように説明するべきか、伝えたい内容をわかりやすく伝える流れを作っていく、その再構築の流れが「構成」です。
この構成の際に、参考にして頂きたいのが、 ID(インストラクショナルデザイン) の考え方です。
おそらくほとんどのクリエイターの皆さんは言葉を知らなくても、この考え方を理解して実践していると思いますが、改めて整理しておくと、実務の際にもスムーズに作業がすすむと思います。
インストラクショナルデザイン(ID)の考え方
教育工学の分野で発展した考え方で、簡単に言えば 「情報を整理して、受け手が理解しやすい順序に設計する手法」
・何を伝えるべきかを明確にする
・受け手の理解度を想定する
・伝える順番と方法を設計する
映像制作でも同じで、ストーリーや構成を考える際に「どうすれば相手に正しく届くか」を設計することが重要です。
詳しくは下記の記事にもまとめています。
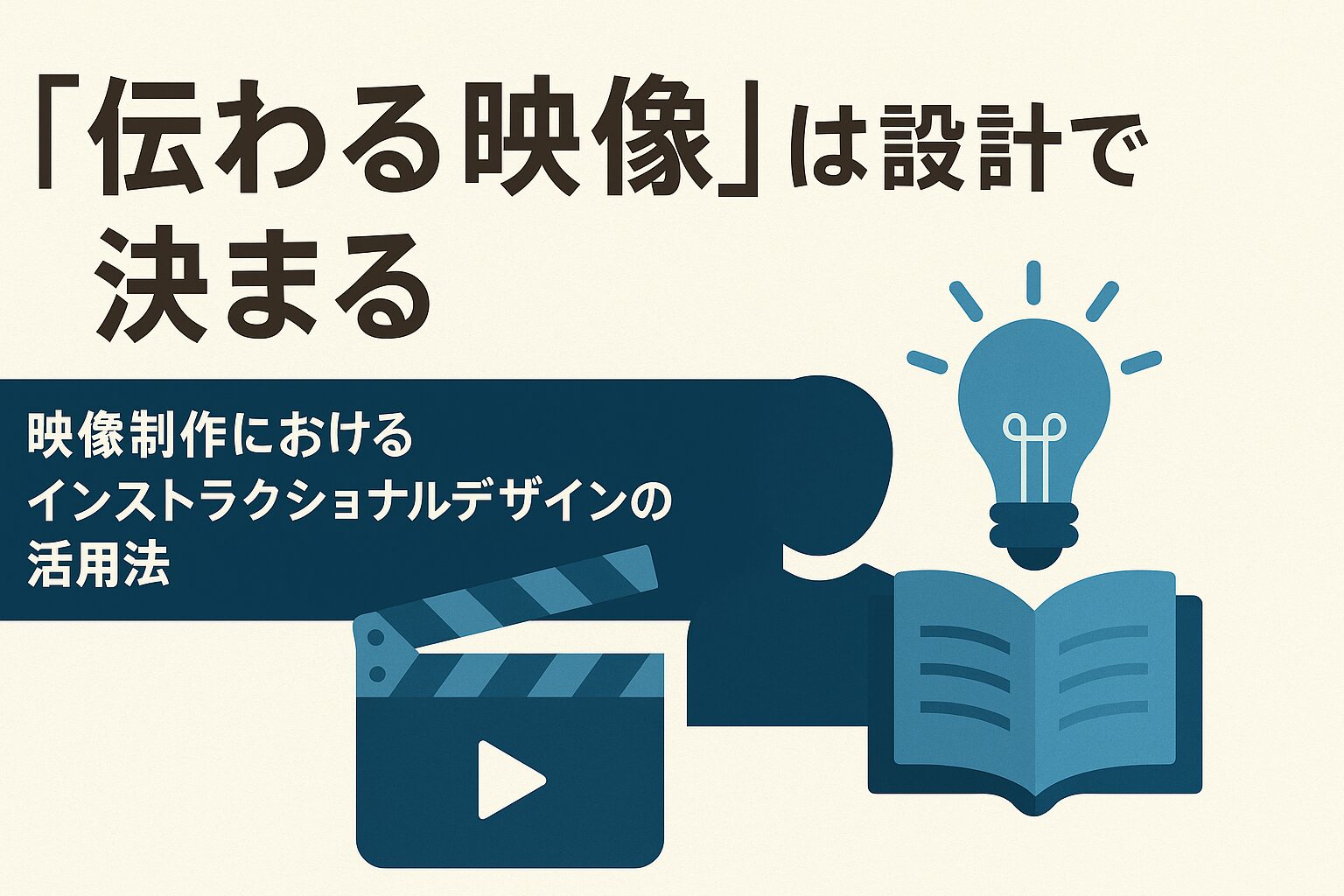
構成により、流れが決まり、その流れに従って、各カットの意味が明確になります。
その与えられた意味・目的に従って、構図やカメラワークが選択されていくことになります。
そのうえで次に求められるのは、映像の要所要所での視認性や伝達力をさらに高める工夫です。
伝達力を補うCGの力
ここで力を発揮するのが CG(コンピュータグラフィックス) です。
CGと聞くと高そう、時間がかかりそう、とネガティブなイメージもあるかもしれませんが、CGを使用することで得られる効果は、そのデメリットを大きく超えるものがあります。ひとつずつ説明していきます。
見えないものを可視化
工業製品の内部構造や、空気や水の流れといった目には見えない現象。実写では表現できない要素を見えるようにします。見えないものは理解が難しいですが、シミュレーションなどでリアルに表現することで、理解度は高まります。見た目のリアルさは視覚的な説得力も高まります。
ポイントを強調
伝えるべき内容が多い映像の中で「どこに注目してほしいか」を明確にするには、強調が有効です。
特定の部分を光らせたり、他を暗くしてフォーカスを集めたり、テキストやアイコンを重ねることで、見る人の意識を自然と導けます。派手な演出ではなく「伝えたいことを強調する」ための工夫が、映像全体の理解度を底上げします。
構造を分解
複雑な構造や仕組みを見せると、受け手はどこをどう理解すればよいか迷ってしまいます。そこでパーツごとに分解し、段階的に見せることで情報が整理されます。
例えば建築や機械の構造説明では、全体像 → 部分 → 再統合という流れをCGで描くと「仕組み」が直感的に伝わります。これは学習教材や取扱説明の映像などでも特に効果的です。
流れを可視化
時間的な流れや、それそれの関連性を視覚的に表現するということもCGが得意とするところです。矢印やラインアニメーションを重ねて「どこからどこへ」「何がどう変化するのか」を見せれば、一目で理解できます。
製造工程やサービスの流れ、システムの仕組みなど、順序や因果が大切な内容を説明する際に「説明不要で理解できる」に変わります。

まとめ
今回は、映像のレベルアップの第一歩として、映像の目的の明確化、構成の整理整頓、そしてその整理された内容を効果的に表現する手法としてCGを使うということをご紹介しました。
映像の目的は、わかっているようでも明確に宣言してしまう方が、のちの作業でブレが生まれませんのでおすすめです。
次に、映像の構成をID(インストラクショナルデザイン)の考え方で整理すること。
何を伝えたいのかを明確にし、受け手の理解の流れを設計することで「伝わる土台」ができます。
そして、整理した内容をより効果的に見せるためにCGを活用すること。
見えないものを可視化したり、注目すべきポイントを強調したり、構造や流れを整理して見せることで、情報はさらに直感的に届きます。
これらの内容を踏まえつつ、映像制作を行うことで、皆さんの映像がレベルアップすることは確実です。
ぜひ、参考にしてみてください。